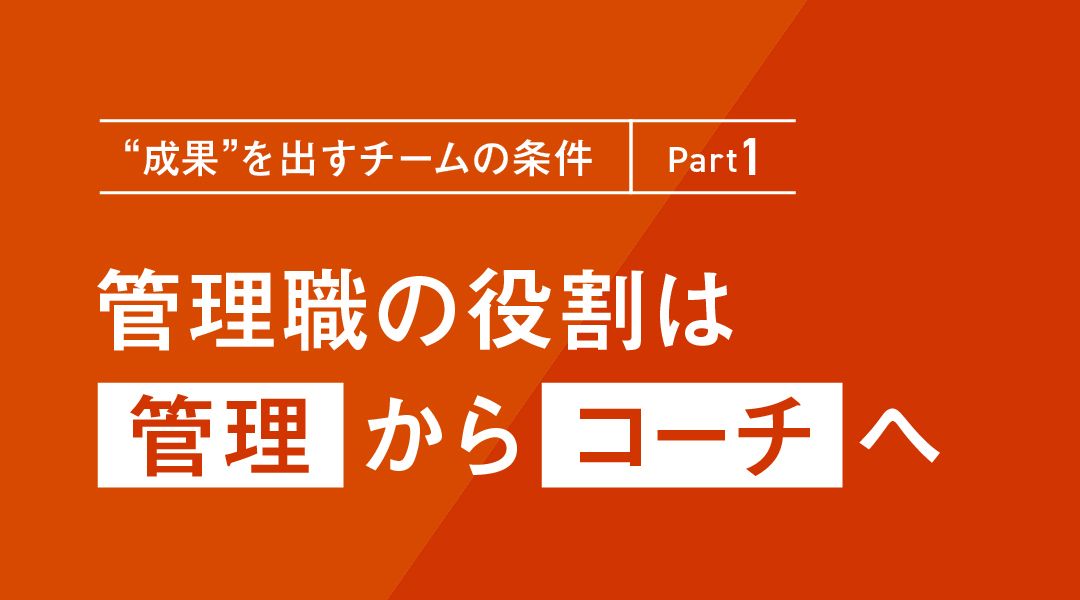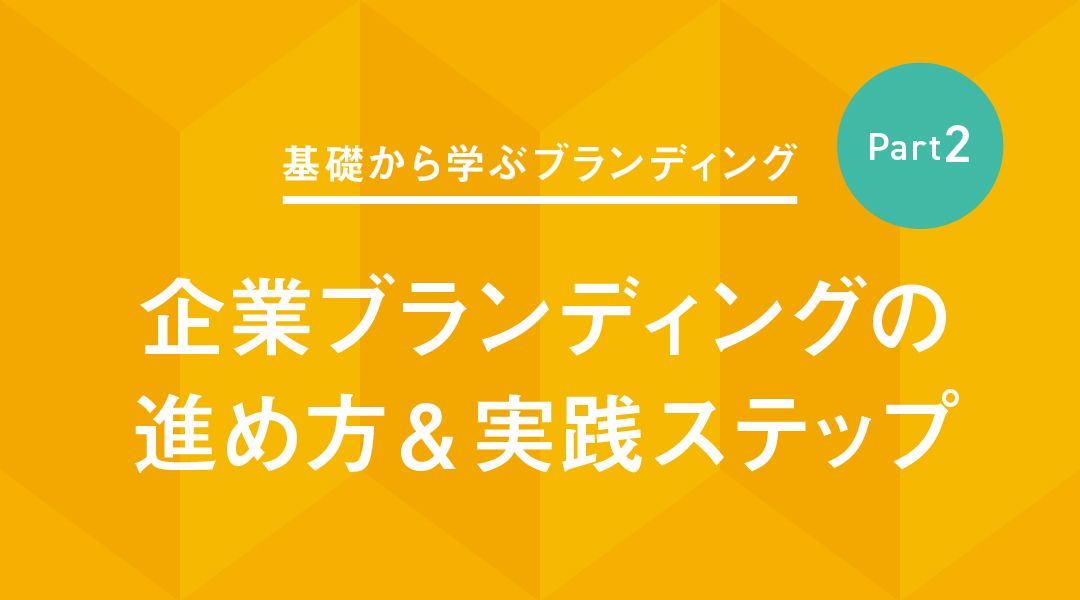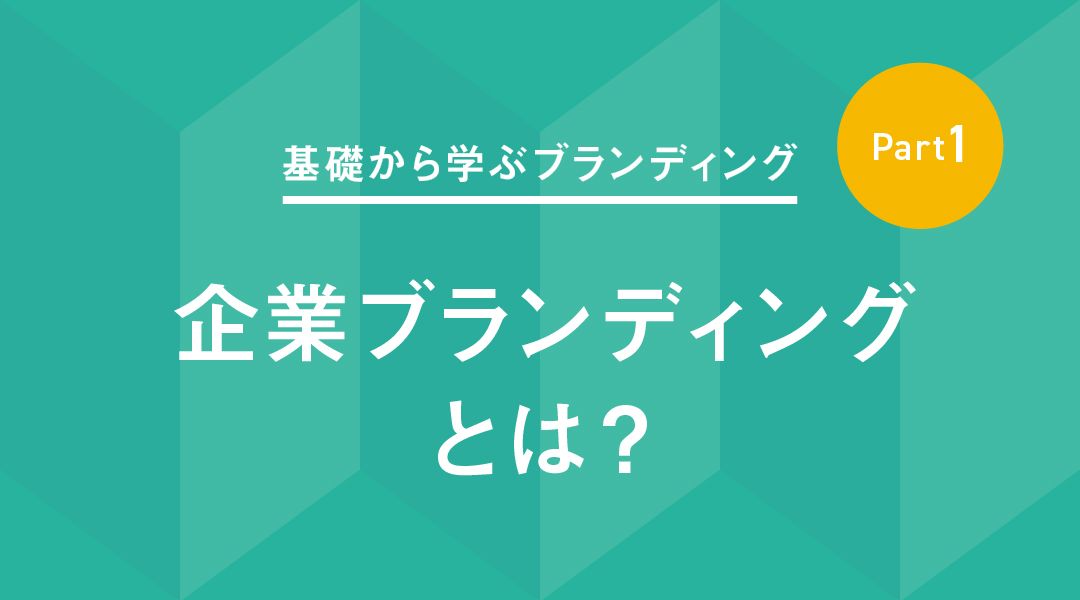組織を強くするOKR運用【Part1. 経営理念が浸透する仕組み】

経営理念を掲げているのに、現場までうまく浸透していない——。 チームの動きに一体感がなく、部署ごとにバラバラに進んでしまっている——。
そんな“目には見えづらいけれど、確かに存在する組織の課題”にどう向き合うべきか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
実は今、「OKR」という目標管理を取り入れることで、業務の進行と経営理念の浸透を両立させる企業が増えています。
本シリーズでは、OKRがもたらす組織変化について、全3回に分けてお伝えします。
“共創の時代”に適した目標管理「OKR」
GoogleやMetaなどが導入したことで注目を集めたのが、「OKR」という目標管理手法。
従来、日本の企業では、目標管理の手法として「MBO」が主流でした。
終身雇用や年功序列を前提とした環境の中で、個人の業務目標を明確にし、人事評価と結びつける目的で導入されたMBO。これは、長期スパンで着実な成果を追うのに適した仕組みでした。
しかし近年、リモートワークの普及や自律型人材の増加により、目標の「見える化」や「全体への共有」がより重視される時代に。そうした背景から、組織のビジョンと現場の行動を結びつけ、部門を超えた連携を可能にするOKRの導入が進んでいるのです。
いずれも組織や個人の目標を明確にし、成果を高めるためのマネジメント手法ですが、考え方や運用方法に違いがあります。
個人の評価のための目標管理。
本人・上司・人事のみに共有される。
(クローズドで個人中心)
【OKR】 組織を一つにするための目標共有。 全社に公開・共有される。 (オープンで共創的)
選ばれるのは“信念のあるブランド”
似たような商品やサービスが溢れる中で、顧客が最終的に選び、ファンになる理由は何か。それは、何を売るかではなく「誰が、どんな想いで届けているか」にあります。つまり、競合との差を生むのは「会社の信念」なのです。
強いブランドをつくるには、価値観や目的を社内で共有し、従業員一人ひとりが“自分ごと”として体現する必要があります。これこそが、インナーブランディングであり、OKRが貢献できる領域です。
「理念は掲げているが、日々の目標や行動とつながっていない」 そんな状態では、ブランドの軸がぶれてしまいます。
経営層から現場まで、共通の目的に向かって動ける組織こそ、理念をブランドとして体現できる組織なのです。
経営理念が“業務の一部”になる仕組み
なぜOKRを導入すると、業務の目標管理と並行して「経営理念の浸透」も進むのでしょうか。 その理由を理解するために、まずはOKRの基本的な仕組みを簡単にご紹介します。OKRとは?
OKRは「Objectives and Key Results(目標と主要な成果)」の略称。「Objective」は目指すべき目的や意義を指し、「何を目指すか(O)」と「どう測るか(KR)」をセットで設定する目標管理手法です。ツリー構造で連動するOとKRの関係
OKRでは、1つのObjective(O)に対して、3つ前後のKey Result(KR)を設定します。まずは会社全体のOとそれを測るKRを決め、それに基づいてチーム単位のOKR、さらに個人単位のOKRへと連動させていきます。このように、組織全体の目標と個人の目標がツリー状に結びついていく構造が、OKRの特徴のひとつです。
短期間・高頻度で運用する
OKRは一般的に3ヶ月単位で運用し、週に1回などのペースで進捗確認を行います。 期間を短く設定することで、優先度の高い目標に絞って集中して取り組むことができます。また、進捗のズレや課題はチーム内・部門間で柔軟に調整しながら、全社的に目標達成を目指すスタイルです。
覚えやすく、共感できる目標設定
会社全体のOは、数値で表現される必要はありません。 誰もが理解しやすく、行動の指針として心に残るような定性的な目標であることが望まれます。定性的・抽象的な目標でも問題ありません。社員全員が目指す方向性に共感しながら、モチベーションを持って取り組めることが重要です。OKRが理念浸透につながる理由
OKRは目標管理の枠を超え、経営理念を“行動に落とし込む”ツールとしても効果を発揮します。 その理由は、以下の3つの特徴にあります。❶目的を重視する
OKRにおける「O」は、単なる業務目標ではなく、なぜそれに取り組むのかという「目的」の意味合いが強くなります。事業の意義や存在理由といった理念に基づくゴールが設定されるため、業務の背景にある「想い」まで含めて共有されるのです。KRは進捗を測るための手段であり、あくまで最終的に目指すのは、その先にある事業の意義や目的となります。❷組織全体でつながる設計
OKRは、会社→部門→チーム→個人へと目標が連動するツリー構造になっています。 この構造によって、個々の業務が会社の目的とどのようにつながっているのかが明確になります。全体が相互につながるので、全員が同じ方向を向くことができます。❸高頻度の対話と振り返り
短い運用期間と週次の進捗確認により、社員全員が常にObjective(目的)を意識した状態で動けるようになります。優先度をつけて集中して取り組み、適切なタイミングで周りと調整することができるのです。その過程で、自分の役割や行動が、会社のO=理念とどう関係しているのかを自然と考える機会が増えます。
これらの特徴から、OKRを導入した組織では次のような変化が生まれます。
⚫︎ 自分の業務と会社のOとの結びつきが見え、理念が“自分ごと”として理解されていく
⚫︎ 進捗確認を通じて継続的に目的を再確認し、理念を軸とした判断・行動が習慣になる
ここまで、
✔️ 強いブランドになるためには、そのブランドを動かす人やチームへの「経営理念の浸透」が必要であること
✔️ 目標管理手法「OKR」を運用すると、業務推進と並行して組織全体への理念浸透ができること
をお伝えしました。
次の記事では、OKRを運用することでインナーブランディングを強化できる理由をもう1つご紹介します。
アドハウスパブリックでは、インナーブランディングをはじめ、新たな商品・サービスや事業開発などブランディングに関するさまざまなサポートを行っています。
競合他社とは一線を画し、圧倒的な支持を集め、一目置かれる存在。すなわち「ブランド」として広く認知されることを目指して、今こそブランディングに取り組みませんか?